FRENCH BLOOM NET 年末企画(2) 2025年のベスト映画
第2弾は2025年のベスト映画です。ちなみにフランスの老舗映画雑誌『カイエ・デュ・シネマ』の2025年のベスト1はアルベルト・セラ(Albert Serra)監督によるTardes de soledadで、闘牛を題材にしたドキュメンタリー映画。ベスト10には、Nouvelle Vague – リチャード・リンクレイター(Richard Linklater)が入っていて、カイエはヌーヴェル・ヴァーグを「運動」ではなく、若者たちの共同的な思考の場として捉えた点を評価。Laurent Dans le Vent (風の中のローラン)というフランス映画も気になる。3人の若い監督による集団制作で、カイエは、説明主義から逃れ、何も語らないことを恐れない勇気が評価されると言う。
不知火検校
東京日仏学院で5月に開催された特別企画「知られざるヌーヴェル・ヴァーグ リュック・ムレ特集」はその後、大阪、京都、神奈川、愛知を10月下旬まで巡回した。2025年のフランス映画関係ではこの企画がメルクマールとも言える重要な出来事となったことは間違いない。その他、フランソワ・オゾンの新作『秋が来るとき』、アルノー・デプレシャンの新作『映画を愛する君へ』など、「ヌーヴェル・ヴァーグ以後」の監督たちの作品が相次いで公開されたことも喜ばしい。ここではフランス映画以外で印象に残った三本を紹介する。
ワン・バトル・アフター・アナザー(ポール・トーマス・アンダーソン監督)
毎回、まったく違うタイプの映画を世に放って観客を唖然とさせるアンダーソン監督の最新作。今回は極左活動家の逃亡劇が極度の緊張感の中で160分以上も続くという作品だ。いつもながら物語は一瞬の緩みもなく進行し、最後の最後まで結論がまったく見えない。主人公の活動家はレオナルド・ディカプリオ、それを追う悪徳軍人がショーン・ペン、そしてベニチオ・デル・トロらが脇を固める。アンダーソンの尋常ではない演出力は今回も冴えに冴えわたり、果てしなく繰り広げられる闘争劇=逃走劇を観客はただ息を詰めて見守るしかない。それにしても、ディカプリオという俳優が非常に個性的な役者へと成長したことには改めて感嘆させられた。この俳優の潜在的な能力は計り知れない。我々はそれを観るためにこれからも劇場に向かわなければならない。
F1/エフ・ワン(ジョゼフ・コシンスキー監督)
トム・クルーズに厚い信頼をおかれ、これまで『オブリビオン』(2013)、『トップガン マーヴェリック』(2022)といった話題作を撮って来たコシンスキーの最新作。ストーリーは単純。引退した筈の天才レーサーが弱小レーシング・チームを救うために現役に復帰、反抗的な若いレーサーを教育し、圧倒的なテクニックを駆使してチームに勝利をもたらす、という話には何の新鮮さもない。しかし、レース場面の描き方・捉え方はこれまでのこの種の映画とは大きく異なっており、観ている者はこのチームの一員としてその場に居合わせているかのような強烈な臨場感を堪能できる。コシンスキーの簡潔な演出、ブラッド・ピットの見事な演技、ハンス・ジマーの圧倒的な音楽、クラウディオ・ミランダの神業的な撮影が完璧に絡まることで、歴史的なレース映画が誕生した。
遠い山なみの光(石川慶監督)
原作者カズオ・イシグロ自身が映像化は難しいと考えていた小説を、次々に話題作を世に送り出して来た気鋭、石川慶が見事に映像化した。核心部分となる「謎」をどう映像化するのかというのが問題となるが、監督・脚本・編集を一手に引き受けている石川は、恐らく観客の多くが納得できるような形で作品を作り上げたのではないか。そして瞠目すべきは二人の主人公、悦子と佐知子を演じた広瀬すず、二階堂ふみの圧倒的な演技力である。この二人に真実味がなければこの作品は成立しようがないが、広瀬と二階堂はまさに「これしかない」というような形で登場人物たちをスクリーンに現前させる。それにより、この映画とその原作が決して正面からは描くことはない1945年8月の長崎に起こった出来事の意味を、見事なまでに観客の心に滲み渡らせる。イシグロ作品の映像化としては『日の名残り』(ジェームズ・アイヴォリー、1993)、『わたしを離さないで』(マーク・ロマネク、2010)がすでにあるが、この作品はそれら以上に成功しているように感じられた。

タチバナ
『ミゼリコルディア』
本場フランスでは、言わずと知れた『カイエ・デュ・シネマ』誌の常連監督らしいので、映画の専門家ではない自分には語るに重いが、サブスクで漫然とアメドラを観ていて連想したのは『殺人を無罪にする方法』(2014-2020)。このドラマは、(フラッシュバックの逆である)フラッシュフォワードというか(ナラトロジーでいう)先説法をうまく使いこなした法廷サスペンスであると同時に、殺人を隠蔽するクライムアクションであり、さらに弁護士やその部下や教え子の法学部生たちに、同性愛者や両性愛者が多く、人物相関図の誰と誰がくっつくか予想がつかないところも醍醐味だった。自分にとってギロディの本作は、この人気ドラマが法曹コミュニティで見せた展開を、フランス田舎町のコミュニティとフランス監督の映画技法でローカライズした作品という印象を受ける。異性愛の規範から解放されると、ラブコメの展開も幅が広がり、ミステリーやクライムアクションにも新鮮な展開が味わえる。本作は、そういう意味で、アンモラルでありながら新たな可能性を感じる作品だった(とはいえ、スリラーとしての不穏さと、ギロディならではのあけすけな性描写を国内の映画館で配給されたインパクトは、『湖の見知らぬ男』の方が大きかったかもしれない)。
『異端者の家』
今年はホラーが豊作だったので、ホラー部門でさえA24の本作を第一に挙げる人は少ないのではないか。若い女性2人が、宗教の訪問勧誘で訪れた屋敷の中年男性に監禁される脱出ゲームのような作品。しかし興味深いのは、ヒロイン2人がカルトと目されがちなモルモン教の若い女性宣教師で、監禁する中年男性がロマコメ名優のヒュー・グラント。宗教に詳しく、徹底して理論武装したグラントが、ヒロイン2人を正論でマンスプしながら追い込んでゆく、ゆがんだ「ディスカッション映画」でもある。どちらの側に立って楽しめばよいのか困惑する凝りに凝ったストーリーは、最後の瞬間までスリリングに練り上げられていてひたすら感心するほかない。グラントの主張は、若者に物を教える側の自分は身につまされる。『ワン・バトル・アフター・アナザー』の合言葉のくだりと同じくらい身につまされた。
『みんな、おしゃべり!』
今年の邦画で真っ先に語りたいのはこれ。しかしつい先日まで、上映館が都内2館と大阪1館だったので見に行くのに苦労した(今は兵庫や福岡や名古屋にも広がりつつある)。関東のどこかの街で、ろう者のコミュニティとクルド人のコミュニティがトラブルになって最後はなんとか収まりのつくある種の長屋物。言語とコミュニケーションをめぐる映画で、テーマが面白い。どちらのコミュニティも一枚岩ではない。ろう者の側には、日本手話と日本語対応手話とアメリカ手話、人工内耳、CODAといろんな内情をかかえる一方、クルド人たちも、トルコ語、クルド語、イスラム語など使える言語がクルド人によって違っていたりする。基本、コメディなのだが、大味なドタバタではない。監督自身がCODAということもあって、今までのろう映画のステレオタイプを巧みに回避しつつ、なにげないセリフの伏線を巧みに回収して、最後はかなり振り切った結末にいたるので、エンタメとしても気軽に楽しめる。ちなみに、パンフレットには、本作の脚本が丸ごと収録されている上に、それ以上に分厚いインタビューページが充実しているので、映画が気に入った人は、パンフもマスト・バイだろう。
なお、本作では、英語やフランス語も登場する。ヒロインが着ているTシャツには「LA CHANCE SOURIT」(幸運〔の女神〕がほほ笑む)というフレーズが胸元にプリントされていて、本作のハッピーエンドの伏線にも思えた。なお、このフレーズをプリントしたTシャツにはバリエーションがあり、改行してもう少し言葉をつなげた「LA CHANCE SOURIT / DU BONHEUR」となっているものもある。ヒロインがどちらを着ていたのか記憶が定かではないが、もしこちらなら、sourire deの用法によって「幸運〔の女神〕は、幸福を面白がる、小ばかにする」という真逆にも取れる皮肉な意味になる。こうしたTシャツの文言とともに、作品の解釈を考察してみるのも楽しいかもしれない。

exquise
生活環境が変わり、ミニシアター系の映画館が遠くなってしまいました。配信サービスもチェックしているものの、家でゆっくり視聴する時間も案外なかったりであまり観られなかった1年でした。
『ワン・バトル・アフター・アナザー』(ポール・トーマス・アンダーソン)
162分の長尺ながら、緩急ある物語に魅了され、時間を感じることなく終盤まで楽しく見られたのだが、原作がT・ピンチョンだとは知らなかった(さらにPTAが彼の作品を映画化したのが2回目だということも)。時代をより現代に寄せて、移民問題など今日的トピックも取り込みながら、かつ親子という普遍的なテーマを描いた作品でもある。撮影もすばらしく、特にカーチェイスのシーンのこれまで見たことない撮り方にゾクゾクした。
ディカプリオは正統派のヒーロー役よりもこういうダメな男を演じた方が面白く、かつ共演する女優二人をとても魅力的に際立たせる要素にもなっている。脇のショーン・ペンのネチっこさやベニチオ・デル・トロのとぼけたような軽さ(でもメッチャカッコいい)も全体のスパイスとなっていて、キャスティングにも大満足。
『7月の物語』(ギョーム・ブラック)
バカンスシーズンのレジャー施設(エリック・ロメールの『友だちの恋人』と同じ舞台)に遊びに来た女性2人をノスタルジックな少し色褪せた明るい風景のもとで描いた第一部と、異国からフランスに留学に来た若者たちとアルメニアから来た救命士らとの交流を描く第二部の構成となっていて、どちらも明らかにロメールを意識した作りになっているが、ロメールのような皮肉っぽさはなくこの監督のもともとの人のよさを感じさせる一方で、撮影中に起きた現実世界の事件の存在がこの映画を単なるオマージュに終わらない(終わらせられない)深みの増した内容にさせている。
演劇学校のワークショップから生まれた作品だそうで、俳優たちは実名で登場しているが、みんなとてもいい味を出している(というか、本当にロメール作品に出てきそうな人たちばかり!)。
『アッテンバーグ』(アティナ・ラシェル・ツァンガリ)
ヨルゴス・ランティモスが製作に加わっているということもあり、一連の彼の作品に通ずる奇妙な設定や登場人物、また独特のユーモアがこの作品でも見られる。登場人物たちの関係性は、人間というよりも動物的であり、主人公のマリーナ(とツァンガリ監督自身)が大好きなリチャード・アッテンボロー(そもそも作品のタイトルがベラが言い間違えた彼の名前なのだ)のドキュメンタリーの動物たちに通じるものがある。
映画はそのような動物的な感覚を持ち続け「人間」に興味を持てないマリーナが、唯一心の拠り所であった父親を失いつつあるなかで、外の世界に少しずつ触れながら独り立ちする(スタートラインにようやく立つ)までが描かれるが、ありふれたビルドゥングスロマンとは程遠い表現にこちらも翻弄されながら最後まで楽しく観た。ところどころに挿入されるベラとマリーナのダンスがたまらなく好きだ。
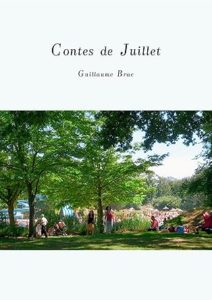
cyberbloom
当サイト の管理人。大学でフランス語を教えています。
FRENCH BLOOM NET を始めたのは2004年。映画、音楽、教育、生活、etc・・・ 様々なジャンルでフランス情報を発信しています。
Twitter → https://twitter.com/cyberbloom